低用量ピルには、避妊や生理痛の軽減、生理不順の改善など、多くのメリットがあります。
一方で、「血栓症のリスクがある」と聞いて不安に感じている方もいるかもしれません。
低用量ピルに含まれる女性ホルモンには血液を固まりやすくする作用があり、ごくまれに血栓症を引き起こすことがあります。
この記事では、低用量ピルによる血栓症のリスクや、血栓症の症状・予防法、症状が起きたときの対処法まで、詳しく解説していきます。
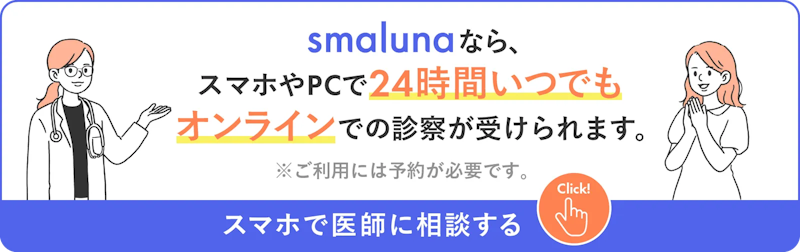
低用量ピルのその他の副作用について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
関連:低用量ピルの効果と副作用|避妊・生理痛・PMSへの影響を詳しく解説
血栓症とはどんな病気?
血栓症とは、血液の一部が固まって血の塊(血栓)となり、血管が詰まってしまう病気です。
足の静脈にできる血栓は「深部静脈血栓症」と呼ばれ、この血栓が肺まで移動すると、「肺塞栓症(エコノミークラス症候群としても知られています)」を引き起こすことがごくまれにあります。
また、血栓ができる場所によっては、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な病気につながってしまう恐れもあります。
低用量ピルの服用により、服用していない場合と比べて血栓症のリスクがわずかに高まることが知られています。血栓症はごくまれな副作用ですが、命に関わることもあるため注意が必要です。
低用量ピルの服用によって血栓症リスクはどのぐらい上がる?
生殖可能年齢の女性において、年間1万人あたりの血栓症発症は、低用量ピルを服用していない場合は1〜5人とされています。
それに対し、低用量ピルを服用している女性では3〜9人と増加するとされています。(参照:OC・LEPガイドライン 2020年度版)
【生殖可能年齢女性の年間1万人あたりの血栓症発症数】
血栓症発症者数 | |
|---|---|
低用量ピルを服用していない | 1~5人 |
低用量ピルを服用している | 3~9人 |
ただ、妊娠中や産後の血栓症のリスク増加と比べると、低用量ピルによる血栓症の発症リスクは相対的には低いことが分かります。
【生殖可能年齢女性の年間1万人あたりの血栓症発症数】
血栓症発症者数 | |
|---|---|
妊娠中の女性 | 5~20人 |
産後12週間の女性 | 40~65人 |
過度に心配しすぎる必要はありませんが、低用量ピルを服用する際には血栓症のリスクや症状について理解を深めておくことが大切です。
血栓症のリスクが高い人の特徴とは?低用量ピルの服用前に要確認
下記に当てはまる人は、健康な人に比べて血栓症のリスクが高くなるとされています。
- タバコを吸う人
- デスクワークや長時間フライトなど、長時間同じ姿勢でいることが多い人
- 高血圧の人
- 肥満の人
- 糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病にかかっている人
- 過去にがん(特に乳がんや子宮体がん)を発症したことがある人
- 脳梗塞などを生じやすい危険な前兆を伴う片頭痛のある人
- 過去に血栓症に関連する病気にかかったことがある人
- 家族が血栓症に関連する病気にかかったことがある人
これらに該当する場合は、低用量ピルの処方を受けられないこともあります。
命に関わるとても大事なことなので、問診では漏れなく正確に申告してください。
※低用量ピルの処方が受けられない方でも、低用量ピルに比べ血栓症リスクが低い「ミニピル」であれば処方が可能な場合があります。
詳しくは診察時に医師までご相談ください。
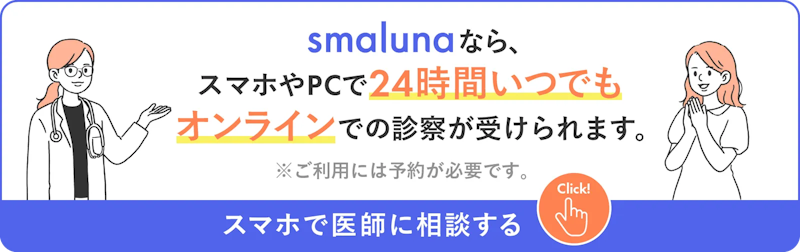
血栓症のリスクはどんなときに高くなる?
脱水、過度の安静、長時間のフライトなどは血栓症のリスク要因とされています。
低用量ピルの内服中は、脱水にならないようにこまめに水分を取るようにしましょう。
※ここでいう水分は、アルコールやカフェインを含むお酒やコーヒー、お茶などを除きます。
また、飛行機など座ったままの時間が長いときには、適宜足を動かしたり、足の動きを妨げないゆったりとした衣服を選ぶことが、エコノミークラス症候群の予防のために有効です。
注意すべき血栓症の初期症状
低用量ピルによる血栓症は、服用開始後3か月〜半年の間に起こりやすいとされています。
血栓症において注意すべき症状としては、「ACHES」という5つの症状があります。
- A(abdominal pain):激しい腹痛
- C(chest pain):激しい胸痛、息苦しい、押しつぶされるような痛み
- H(headache):激しい頭痛
- E(eye/speech problems):視覚の異常(見えにくい所がある、視野が狭くなる)、舌のもつれ、失神、けいれん、意識障害
- S(severe leg pain):ふくらはぎの痛み・むくみ、熱感の増加や皮膚の赤み
こうした症状が現れたら、すぐにピルの服用を中止し、医療機関を受診してください。
低用量ピルの服用中に血栓症の症状が出たときの対処法は?
血栓症の症状を自覚した場合は、すぐに服用を中止し、処方を受けた医師、もしくは近くの医療機関に相談しましょう。
もし処方を受けた医療機関とは別の場所を受診された場合は、必ず「低用量ピルを服用していること」を診察する医師へ伝えてくださいね。
もし血栓症を発症しても早期に適切な治療を受けることができれば、ほとんどの方は命にかかわることはありません。
そのため、症状に気付いたらそのままにせず、早めに医療機関を受診しましょう。
また、低用量ピルの服用中には、半年に1回程度の血液検査のほか、子宮頸がん・乳がん・性感染症検査などの婦人科検診も定期的に受けることをおすすめしています。
よくある質問
低用量ピル服用中の血栓症の初期症状は?
血栓症には以下の症状が関連するとされています。
- A(abdominal pain):激しい腹痛
- C(chest pain):激しい胸痛、息苦しい、押しつぶされるような痛み
- H(headache):激しい頭痛
- E(eye/speech problems):視覚の異常(見えにくい所がある、視野が狭くなる)、舌のもつれ、失神、けいれん、意識障害
- S(severe leg pain):ふくらはぎの痛み・むくみ、熱感や皮膚の赤み
こうした症状が現れた場合は、すぐに低用量ピルの服用を中止し、医療機関を受診してください。
低用量ピルの服用によって血栓症の発症確率はどのぐらい上がりますか?
生殖可能年齢の女性の場合、ピルを服用しない場合の血栓症発症数は年間1万人あたり1〜5人であるのに対し、ピルを服用している場合は3〜9人と上昇するとされています。
上昇率としてはわずかで過度に心配しすぎる必要はありませんが、症状が現れた場合はすぐに医療機関を受診するようにしてください。
血栓症は予防できますか?
血栓症は、脱水や長時間座ったままの姿勢でいることなどがリスク因子とされています。
こまめに水分を取り、座った時間が長い時には適宜足を動かすことが予防につながります。
また、自己判断で低用量ピルの中止と再開を繰り返すことは血栓症のリスクを高める可能性があるため、必ず医師の指導のもとに服用するようにしてください。
まとめ
この記事では、低用量ピルによる血栓症のリスクや症状、対処法について詳しく解説しました。
血栓症はごくまれな副作用ですが、初期症状に気をつけておくことが大切です。もし激しい胸痛やふくらはぎの痛み・腫れなどの症状を感じた場合は、すぐに医療機関に相談してください。
低用量ピルを安全に使用するためにも、事前にリスク要因を確認し、自分の健康状態に合った選択をすることが重要です。
参考文献・資料
- 「OC・LEPガイドライン 2020年度版」日本産婦人科学会/日本女性医学学会,2020年
- 「産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編2023」日本産婦人科学会/日本産婦人科医会,2023年
- 「血栓症ガイドブック」一般社団法人 日本血栓止血学会,2025年8月閲覧

