「生理がきそうでこない」
「下腹部痛があるが生理がなかなか始まらない」
そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
生理前のような症状があるのに出血が始まらない場合、ホルモンバランスの乱れや妊娠、疾患、体調の変化など、さまざまな原因が考えられます。
この記事では、生理が遅れる原因やセルフチェック方法、なかなか生理がこないときの対処法まで詳しくご紹介していきます。
「病院に行くほどではないかも…」「まずは誰かに相談したい」
という方は、オンラインでの診察や助産師・薬剤師への相談ができるスマルナアプリもご活用ください。
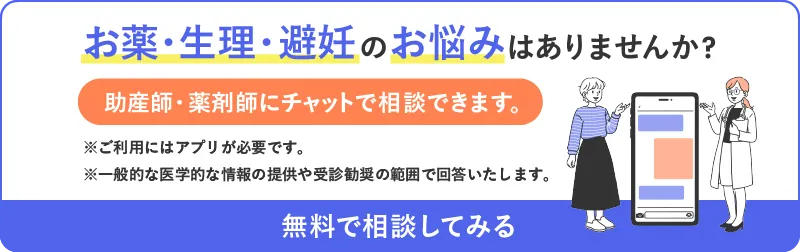
生理がきそうでこないときのセルフチェックポイント
「生理が来ない」と感じたときは、まず落ち着いてご自身の体の変化を振り返ることが大切です。
以下のセルフチェックを活用して、生理周期や体調について確認してみてください。
いつから、どのくらい遅れているかを把握する
まずは生理の遅れを正確に把握するために、直近の生理開始日と生理周期を振り返りましょう。
生理周期とは、生理が開始した日から次の生理開始日の前日の日数のことです。
日本においては、正常な生理周期の範囲は25日~38日とされています。(参照:「産婦人科診療ガイドライン -婦人科外来編2023」)
正常範囲より生理周期が短い場合を「頻発月経」、長い場合を「希発月経」と呼びます。
数日~7日程度のずれはよくあることで、問題ないことがほとんどです。
一方、1週間以上の遅れがある場合や、周期が毎回大きく異なる場合は、何らかの原因が隠れている可能性があります。
アプリや手帳などで月経日を記録する習慣を持つと、変化に気づきやすくなります。
妊娠の可能性をチェックするには?
妊娠の可能性がある方は、妊娠検査薬を使って早めに確認しましょう。
市販の妊娠検査薬は、生理予定日の1週間後(=生理が7日以上遅れている場合)から正確に判定できる確率が高まります。
※生理予定日がわからない場合は、性行為から3週間後以降の検査をおすすめします。
陽性反応が出た場合は、できるだけ早めに産婦人科を受診しましょう。
陰性でも生理が来ない状態が続く場合は、排卵の遅れや検査時期の誤差が原因のこともあるため、数日空けて再検査を行うのがおすすめです。
基礎体温の変化から排卵の有無を知る
基礎体温を記録することで、排卵の有無やホルモンバランスの変化を推測することができます。
正常な排卵がある場合、体温は「低温期→排卵→高温期」と変化していきます。
基礎体温の変化 | 考えられる体の状態 |
|---|---|
低温期・高温期の二相性 | 正常範囲 |
高温期が持続して生理がこない | 妊娠の可能性がある |
体温が安定していて変化がない | 排卵がない可能性がある |
基礎体温は毎朝決まった時間に測定し、1か月単位で記録することが重要です。
基礎体温変化は小さく普通の体温計では正しく測定できないため、専用の基礎体温計をご使用ください。
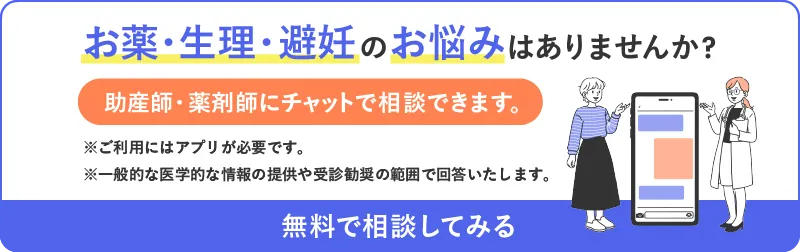
生理がきそうでこないときに考えられる6つの原因
生理が遅れたり、周期が乱れる理由は多岐にわたり、必ずしも妊娠が原因とは限りません。
続いては、生理がきそうでこないときに考えられる主な原因について解説していきます。
①ホルモンバランスの乱れ
生理は、脳の視床下部・下垂体・卵巣が連携して女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)を分泌することでコントロールされています。
ストレスや生活習慣の乱れがあると、排卵が遅れたり生理が来なくなったりすることがあります。
特に、過度なストレス・急激なダイエット・睡眠不足などは、ホルモンの分泌に影響を与えやすい要因です。
「生理前のような下腹部痛や胸の張りがあるのに出血しない」といったケースでは、こうしたホルモンの乱れが原因となることも少なくありません。
②妊娠の可能性
生理周期が安定している方で「生理がきそうでこない」場合、妊娠の可能性についても確認をしておきたいです。
生理前と妊娠超初期は、どちらもホルモンの影響で体に似たような変化(下腹部の痛みや違和感、胸の張り、眠気など)が起こる可能性があり、区別がつきにくいことがあります。
妊娠の可能性があり、生理予定日から1週間以上経っても出血がない場合は、市販の妊娠検査薬を使用してみましょう。
検査のタイミングによっては陰性でも、後日陽性となるケースもあるため、再検査や産婦人科での受診が必要になることもあります。
③更年期の影響
40代以降になると、女性ホルモンの分泌量が徐々に変化し、排卵のタイミングや生理周期が不規則になることがあります。
更年期は閉経前後の約10年間を指し、個人差がありますが、40代前半から兆候が現れる方もいます。
生理がきそうでこない・周期がバラつく・出血量が変わるなどの変化に加え、のぼせ、イライラ、不眠などの症状を伴う場合は、更年期が原因である可能性を考慮しましょう。
④お薬の影響
ピルやホルモン剤、抗うつ薬、抗精神病薬など、一部の医薬品はホルモンバランスに作用し、生理が遅れる原因になることがあります。
特に、低用量ピルを服用している場合は、子宮内膜が薄く保たれるため、生理がこない・出血が極端に少ないこともあります。
また、服薬を自己判断で中止・再開した場合にも、ホルモンの変化により生理が不安定になることがあります。必ず、処方した医師の指示に従って服薬をするようにしましょう。
⑤甲状腺の病気
甲状腺は全身の代謝をコントロールする臓器で、異常があると生理周期にも影響します。
甲状腺機能が低下する「甲状腺機能低下症」では、無月経や生理の遅れが起こることがあり、逆に機能が過剰になる「甲状腺機能亢進症」でも周期の乱れが見られます。
これらの病気では、倦怠感、体重変化、寒がり・暑がり、脈の異常など、他の全身症状を伴うことが多いため、気になる変化がある場合は内科や婦人科への受診を検討しましょう。
⑥子宮・卵巣の病気
子宮や卵巣に何らかの疾患があると、生理周期に影響が出ることがあります。代表的なものに、子宮筋腫、卵巣嚢腫、卵巣機能不全などがあります。
これらの疾患は、生理が不規則になるだけでなく、経血量の増加、強い生理痛、下腹部の違和感、腰痛などを引き起こすこともあります。
長期間生理が来ない、あるいは痛みや出血が普段と違うと感じる場合は、婦人科への相談をおすすめします。
生理がきそうでこないときの対処法まとめ
ここでは、生理がきそうでこないときの対処方法をまとめます。
問題がないケース:1週間程度の遅れ
生理がきそうでこないときは、まずは落ち着いて様子を見ましょう。
1週間以内の遅れであれば、問題ないことがほとんどです。
また、ストレス、睡眠不足、過度なダイエットや運動などはホルモンバランスを崩す要因です。
体と心をしっかり休めること、栄養バランスの良い食事、適度な運動を心がけることが、生理周期を整えることにつながります。
ただし1週間以上生理が遅れていて妊娠の可能性がある場合は、念のため妊娠検査薬で妊娠していないかの確認を行いましょう。
受診を検討した方がいいケース:1週間以上の遅れや気になる症状がある
一方で、以下のような症状がある場合は、自己判断せずに婦人科で医師の診察を受けるようにしましょう。
- 生理が1週間以上来ない
- 腹痛・吐き気・不正出血など他の症状を伴う
- 妊娠検査薬で陽性が出た/判定が曖昧
- 毎月周期の乱れが繰り返される
生理に伴う症状で不安なことはスマルナで相談しよう
生理周期は個人差も大きいですが、生理予定日から1週間以上のずれが頻繁に起きる、我慢できない痛みやいつもと違う出血があるといった場合は、思わぬ不調が隠れているケースもあります。
スマルナではオンラインで医師の診察を受けられるだけではなく、薬剤師や助産師などの専門家から無料でアドバイスを受けられます。生理に伴う症状で不安なことがある方は、ぜひスマルナにご相談ください。
※スマルナ医療相談室のご利用にはスマルナアプリが必要です。スマルナ医療相談室では、一般的な医学的な情報の提供や受診勧奨の範囲で回答いたします。
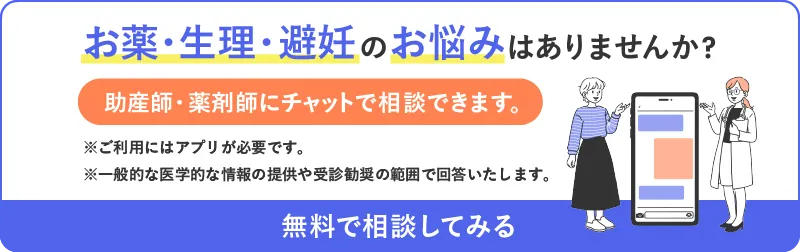
よくある質問
生理がきそうでこないときはどうすればいい?
1週間程度の遅れであれば、問題がないこともほとんどです。
正常な生理周期のためには、食生活を改善したり、適度な運動を取り入れること、ゆっくりお風呂に入ってリラックスすることなどが、日常でできる対策となります。
1週間以上生理が遅れる場合は、念のため妊娠検査薬を試しましょう。
また、生理周期が39日以上であることが続いたり、3か月以上生理が来ないといったケースでは、早めに婦人科を受診しましょう。
生理がきそうでこないときに腹痛があるのはなぜ?
生理前に下腹痛がある場合、PMSの症状や排卵痛など、さまざまな要因が考えられます。
痛みが腰や背中にも広がってくる場合や、我慢できない痛みの場合は無理せずに婦人科を受診するようにしましょう。
生理がきそうでこないときに早くこさせる方法は?
生理は女性ホルモンでコントロールされているため、自力で早くこさせる・ずらすといったことはできません。
旅行やイベントなどで先の予定の生理をずらしたいという方は、婦人科や医療機関で処方を受けられる中用量ピルの使用もご検討ください。スマルナでも中用量ピルの処方を行っています。
生理前にイライラやだるい、吐き気といった症状があるのはなぜ?
月経前症候群(PMS)では、生理前3~10日ごろの時期に様々な精神的・身体的な症状が現れることがあります。
【PMSの主な症状】
- 胸の張り
- 下腹部の張り
- むくみ
- 疲労感
- 頭痛
- イライラや気分の変化
生理前に気になる症状がある場合は、一度婦人科で相談してみてください。

