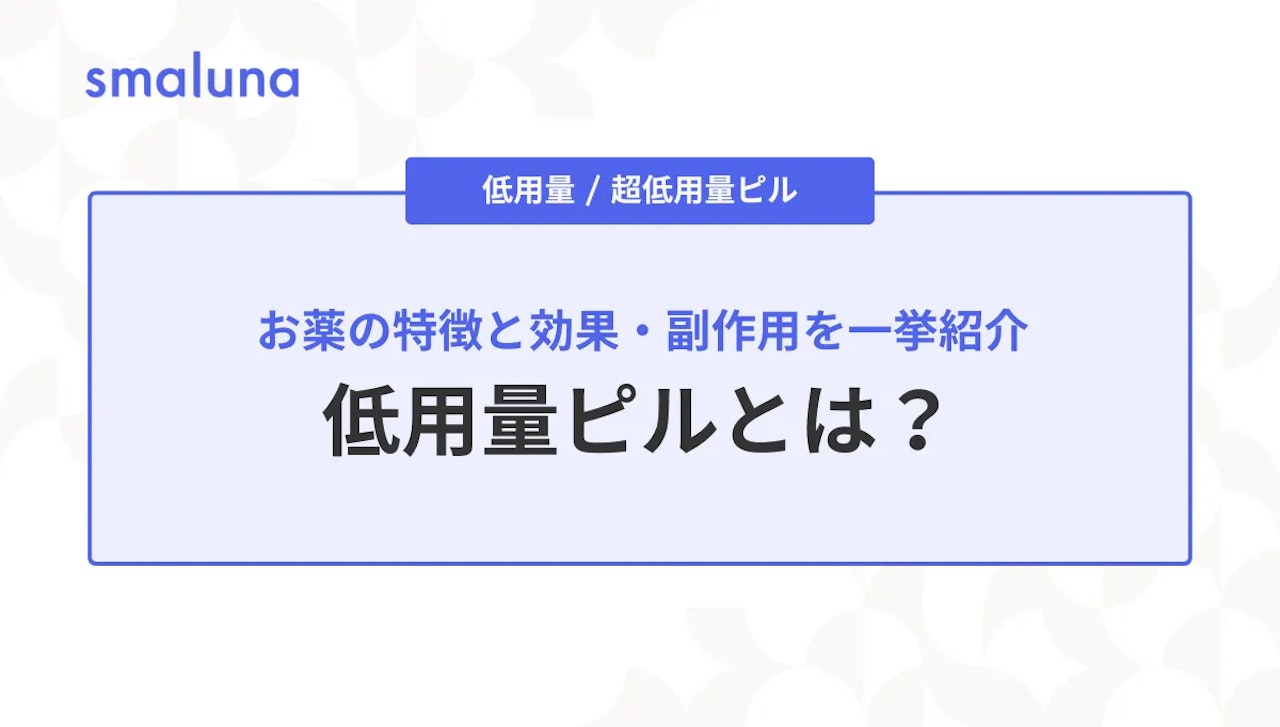低用量ピルは、避妊だけでなく、生理痛の軽減や生理不順の改善、PMS対策、肌トラブルの改善など、さまざまな目的で使われているお薬です。
一方で、「副作用は大丈夫?」「いつから効果が出るの?」「値段や入手方法は?」といった不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、低用量ピルの基本的な仕組みから、期待できる効果、副作用やリスク、正しい飲み方まで、はじめての方にもわかりやすく丁寧に解説します。
自分に合った選択をするための判断材料として、ぜひ参考にしてください。
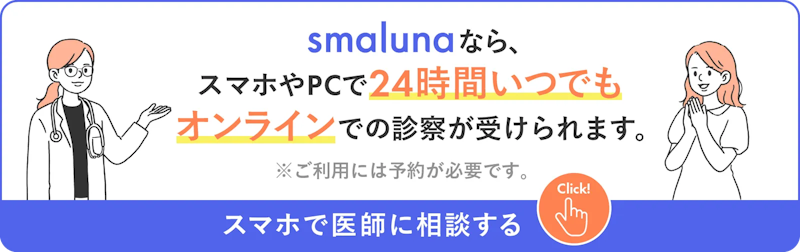
低用量ピルとはどんなお薬?
低用量ピルとは、卵胞ホルモンと黄体ホルモンという2種類の女性ホルモンが少量配合されたお薬のことです。
1日1錠を適切に服用することで、高い避妊効果が期待されます。
また、避妊のみならず、生理痛や生理不順、過多月経、PMSの改善など、女性の健康をサポートする様々な効果が期待できるとされています。
低用量ピルの種類|OCとLEPの違い
日本では、避妊を目的とした低用量ピルを「OC」、月経困難症や子宮内膜症などの治療を目的とした低用量ピルを「LEP」として区分しています。
成分はほぼ同じですが、処方の目的や保険適用の扱いが異なります。
| OC | LEP |
|---|---|---|
主な処方目的 | 避妊目的 | 治療目的 |
保険適用 | すべて自費 | 保険適用あり |
有効成分 | 卵胞ホルモンと黄体ホルモン | 卵胞ホルモンと黄体ホルモン |
※スマルナの提携医療機関で受診の場合は、低用量ピルの処方はすべて自由診療(保険適用外)です。
OC・LEPのどちらも、処方には医師の診察が必要です。
低用量ピルの服用方法
低用量ピルは、毎日1錠を決まった時間に服用します。
低用量ピルには、21錠タイプと28錠タイプがあり、偽薬(プラセボ)の有無、休薬期間の過ごし方が異なります。
21錠タイプの場合
21錠の実薬(ホルモンが入っているお薬)を毎日決まった時間に服用し、7日間休薬します。
その後、次のシートを飲み始めます。
28錠タイプの場合
21錠の実薬を毎日決まった時間に服用し、7日間はホルモンの成分が入っていないプラセボ(偽薬)を服用します。
1シート服用が終わったら、次のシートを飲み始めます。
なお、プラセボは飲み忘れを防ぐために用意されており、飲み忘れても問題ありません。もし飲み忘れた場合はその1錠を破棄しましょう。
低用量ピルの効果・副効用
ここでは、低用量ピルの効果や、服用することによって副次的に得られるメリットをご紹介します。
- 生理不順の改善
- 生理日の移動(月経移動)
- 生理痛の軽減
- 過多月経の軽減
- 月経前症候群(PMS)の緩和
- ニキビや肌荒れの改善
- 子宮内膜症の悪化予防
- 卵巣がん・子宮体がんの発生リスクの軽減
①避妊効果
低用量ピルを服用すると排卵が抑えられ、また子宮内膜が薄く保たれることで受精卵が着床しにくい状態となり、妊娠を防ぐことができます。
ただし、飲み忘れたケースでは避妊効果が下がってしまうことが懸念されるため、毎日規則正しく服用することが大切です。
②生理不順の改善
低用量ピルを服用すると、ホルモンバランスが整うことで規則的な月経周期に近づきます。
休薬(偽薬)の期間に出血が起こるため、生理周期をコントロールしやすくなるメリットがあります。
③生理痛の軽減
生理のときには子宮内膜から「プロスタグランジン」という子宮を収縮させる物質が分泌されており、これが過剰に分泌されることが痛みの原因となっています。
低用量ピルは子宮内膜が厚くなるのを抑えるため、プロスタグランジンが作られにくくなり、生理痛がやわらぐと言われています。
ピルの副効用としての生理痛の軽減については、こちらの記事でも解説しています。
関連:ピルは生理痛に効果がある?服用方法や症状が変わらないときの対処法
④月経移動
大事な予定と生理がかぶってしまいそうなときは、生理開始日を移動させること(月経移動)ができます。
普段低用量ピルを飲んでいない方の生理日移動には中用量ピルが多く使われますが、低用量ピルを継続して服用中の方は、低用量ピルを使用した月経移動が可能な場合があります。
お薬の種類や、生理をずらしたい日数などによって飲み方が異なるので、自己判断はせず処方医に確認してください。
関連:低用量ピルで生理をずらす方法|月経移動に関する知識を徹底解説
⑤過多月経の軽減
生理のときの経血量には個人差も大きいですが、正常な出血量としてはナプキンを2時間に1回変える程度の量が目安となります。
それよりも頻繁に交換が必要な場合は、過多月経が疑われます。
低用量ピルには子宮内膜を薄く保つ働きがあるため、生理のときの出血量を減少させることができるとされています。
⑥月経前症候群(PMS)の緩和
月経前症候群(PMS)は、生理前3〜10日間に出現する身体的・精神的な様々な症状のことです。
【PMSの主な症状】
- 疲労感
- むくみや体重増加
- 腰痛や頭痛
- 気分の変化やいらいら
- 抑うつ気分
これらの症状は、生理が来ると弱まる、または消失することも特徴です。
PMSより症状が重い場合は月経前不快気分障害(PMDD)とされ、こちらは精神症状が主となります。
月経前症候群(PMS)の原因は詳しく分かっていませんが、一部の低用量ピル(成分により差があります)で、PMS/PMDDの症状が軽くなる方もいます。
※効果には個人差があり、日本でPMS/PMDDを適応としていない製品もあります。
⑦ニキビや肌荒れの改善
生理前や生理中にニキビができて悩んでいる方も多いと思いますが、これはホルモンバランスの変化が影響しているといわれています。
低用量ピルの服用を継続することで、体内のホルモンバランスが整い、ニキビを改善する効果が期待できます。
人によってはピルを飲み始めた時期に副作用として肌荒れが起こるケースもありますが、ほとんどの場合は一時的なもので、3ヶ月ほど飲み続けることで改善することが多いとされています。
⑧子宮内膜症の悪化予防
子宮内膜症は、本来あるべき場所(子宮の内側)以外の場所(卵巣など)に子宮内膜が発生してしまう病気で、重い生理痛や不妊の原因となることもあります。
子宮内膜症の治療として、痛みに対しては鎮痛剤が使用され、鎮痛剤の効果が乏しい場合には低用量ピルや黄体ホルモン剤が使用されます。
低用量ピルには子宮内膜の増殖を防ぐ作用があり、子宮内膜症の予防や治療の効果があるとされています。
⑨卵巣がん・子宮体がんの発生リスクの軽減
低用量ピルは、一部のがんの発生リスクを軽減する効果が期待できるとされています。
卵巣がんは発見しにくく進行の速い、悪性度の高いがんです。
繰り返し起こる排卵によって卵巣の壁がダメージを受けることが原因の1つ。ピルによって排卵が抑制されるため、卵巣への負担が減り、卵巣がんのリスク軽減が期待できます。
また、子宮体がんとは子宮の内側にできるがんです。
子宮体がんは、子宮内膜増殖症から進行することがあり、ピルによって子宮内膜の増殖を抑えることで予防効果があるとされています。
ただし100%発症を防げるものではないので、定期的に婦人科で検査を受けるようにしましょう。
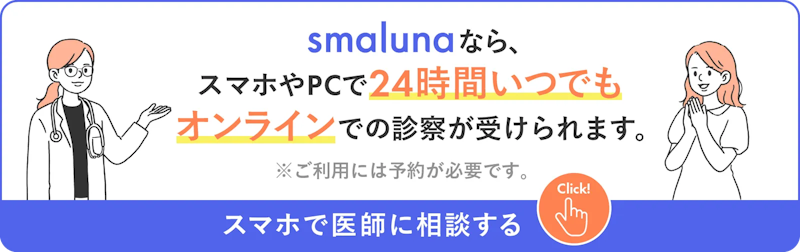
低用量ピルの副作用とリスク
低用量ピルの主な副作用とリスクは、次の通りです。
- 不正出血
- 吐き気
- 血栓症
- 乳がん・子宮頸がんの発生リスクを増加させる可能性
①不正出血
不正出血は、低用量ピルの副作用として最も多い症状とされています。
特に飲み始めから1〜3か月目の時期に起こりやすく、服用を継続することで症状が落ち着いていくことが多いとされています。
少量の出血であれば過度に心配する必要はありませんが、以下のようなケースでは医師に相談を行いましょう。
- 服用開始から4か月目に入っても出血がおさまらない
- 1か月以上連続して不正出血が続く
- 強い腹痛を伴う
※避妊効果を保つためにも自己中断は避け、気になる場合は医師にご相談ください。
関連:低用量ピルの不正出血はなぜ起こる?出血が続く原因や対処法を解説
②吐き気
ピルの服用によって女性ホルモンのバランスが変化し、吐き気の症状が起こることがあります。
ピルは、超低用量ピル、低用量ピル、中用量ピルの順に配合されているホルモンの量が多くなり、吐き気も起こりやすくなります。
低用量ピルでは、3か月ほどの服用継続で症状がおさまることが多いとされています。
吐き気がつらい場合は市販の吐き気止めとピルを併用できることもありますが、自己判断せずに医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
関連:ピルの副作用で吐き気がする際の対処法|症状が改善されないときは?
③血栓症
血栓症とは、血管内にできた血の塊(血栓)が血流をさまたげることによって起こる病気です。
血栓ができる場所によっては、重篤な症状を引き起こすこともあります。
ピルを服用する人は、服用していない人に比べて血栓症を発症するリスクが増加するとされており、特に服用初期の数か月間に注意が必要です。
以下のような症状が現れた場合は、すぐにピルの服用を中止して医師に相談を行いましょう。
- 息苦しい
- 胸がひどく痛い
- 頭がひどく痛い
- お腹がひどく痛い
- 手足がしびれる
- ふくらはぎがむくんだり痛みがある
また、喫煙者の方や40歳以上の方など、血栓症のリスクが高い方では慎重投与、またはピルを処方できない場合があります。
低用量ピルは安全性が高く、安心して服用することのできるお薬ですが、医師の処方のもと適切に服用することが大切です。
関連:ピルの重大な副作用「血栓症」とは?リスクや症状について解説します
④乳がん・子宮頸がんのリスク
低用量ピルの服用により乳がんのリスクがわずかに上昇するという報告があり、中止後は時間とともにリスクが低減するとされています。
関連:ピルを飲むと乳がんになりやすい?リスクの真実と正しい知識を解説
一方で、卵巣がん・子宮体がんについては、リスクはむしろ低下傾向となります。
また、子宮頸がんについては、主要な原因はHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染とされていますが、低用量ピルの5年以上の服用で子宮頸がんの発症リスクが上昇する可能性が指摘されています。
低用量ピルの服用の有無にかかわらず、子宮頸がん予防には、はじめての性交渉前のHPVワクチン接種、性交時のコンドーム使用が有効です。
※はじめての性交渉後の方も、できるだけ早期にHPVワクチンを受けることで子宮頸がんのリスクを下げることができる可能性があります。
関連:ピルで子宮頸がんリスクは上がる?影響の程度と正しい予防法を解説
乳がん・子宮頸がんともに、ピル以外の要因によっても影響を受けるため、早期発見・対処のためには定期的に検診を受けることが重要です。
低用量ピルを服用できない人
体質や生活習慣によっては、低用量ピルを処方することができない、または慎重投与となることがあります。
低用量ピルの処方が難しいと判断される例の一部をご紹介します。
- 40歳以上でピルを初めて処方される方、49歳以上の方
- 35歳以上で1日15本以上タバコを吸う方
- お薬の成分に対し過敏症の既往歴がある方
- 高血圧(160/100mmHg以上)の方
- 糖尿病の方
- 妊娠中、授乳中の方
- 前兆のある片頭痛の既往歴がある方(せんき暗点、星型せん光など)
- 乳がん、子宮体がん、子宮頸がんの既往歴がある方
- 血栓症のリスクがある方
低用量ピルの服用を検討している方は、まずは医師にご相談ください。
よくある質問
低用量ピルを服用すると妊娠しにくくなる?
低用量ピルを服用しても、将来的に妊娠しにくくなることはありません。
ピルは排卵を抑制して一時的に妊娠しづらい状態とするお薬であり、服用をやめれば再び排卵が起こります。
「将来妊娠したい」と考えている方でも、低用量ピルは安心して服用することができるお薬です。
関連:ピルを飲むと将来妊娠できなくなる?ピルと妊娠の関係を解説します
低用量ピルを服用すると太る?
ピルの服用と体重増加には、因果関係はないということが研究で分かっています。
ただ、ピルの服用開始時期には、一時的にむくみや食欲の変化が起こることがあります。
服用を継続することでホルモンバランスが落ち着き、症状が自然と軽快することが多いとされています。
まずは3シートほど服用を継続して様子を見てみましょう。
関連:低用量ピルを服用すると太るの?体重増加を感じたときの対処法は?
40代でも低用量ピルを服用できますか?
健康な女性であれば、50歳または閉経を迎えるまでは低用量ピルを服用することができるとされています。
ただし、加齢に伴って血栓症などのリスクが高まるため、個別の服用可否については、医師にご相談ください。
関連:ピルは何歳まで飲める?閉経や更年期との関係や年代別の注意点まで解説
低用量ピルを購入するには?
低用量ピルの処方には、医師の診察が必要です。
医療機関に足を運んで対面診察で処方してもらう方法と、オンライン診察で処方してもらい自宅でお薬を受け取る方法があります。
関連:低用量ピルってどうやって処方してもらうの?対面診察・オンライン診察を一挙紹介!
低用量ピルは保険適用ですか?
避妊目的で処方される低用量ピルは、すべて保険適用外です。
月経困難症や子宮内膜症などの治療目的で、医師が必要と判断した場合には保険が適用されます。
スマルナの提携医療機関で受診の場合は、すべて自費診療(保険適用外)となります。
低用量ピルの1か月あたりの値段は?
避妊目的での低用量ピルの処方はすべて保険適用外で、自費診療での処方となります。
お薬の種類にもよりますが、低用量ピル1シートあたりの料金は、3,000円~4,000円台が相場です。
お薬の費用に加え、診察料や検査を行った場合の費用、オンライン診察の場合は送料などが別途発生する場合があります。
治療目的で医師が必要と判断した場合は保険適用となり、より安価にお薬を購入することができます。
参考文献・資料
- 「OC・LEPガイドライン 2020年度版」日本産婦人科学会/日本女性医学学会
- 「産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編2023」日本産婦人科学会/日本産婦人科医会
- 「月経前症候群・月経前不快気分障害に対する診断・治療指針」日本産婦人科学会 女性ヘルスケア委員会 2023-2024年度